 アクセス・お問い合わせ
アクセス・お問い合わせ 資料請求
資料請求
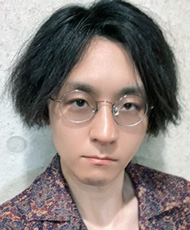
社会人として働きながらの学習は時間的な制限がありますが、オンラインでの授業であればパソコン1台で職場や自宅などどこからでも授業が受けられるため、移動時間等の無駄がなく必要なことに集中して時間を使うことができます。特に私のような交通の便が悪い地方の学生にとっては大変ありがたい環境です。また、オンラインでの授業は資料が画面共有されるためどこを説明しているのかも分かりやすく、急な仕事で授業に参加できなかった場合や1回だけの受講では理解が及ばなかった場合にも、後日講義動画を視聴することで次回の授業に追いつけるようになるなど通学での授業にはないメリットがオンライン授業にはあると思います。
どの科目も税理士試験の受験勉強では得られない知識や視点を身につけることができますが、特に「租税法事例研究」や「経営事例研究」などの応用実践科目の履修が今後の税理士としての働き方に大きな影響を与えてくれたと感じています。「租税法事例研究」では、税理士試験で扱わない「租税法の解釈」について、どのような点で実際に争われてきたのか、また、自分ならばどの様に解釈するのかを思考することにより、同じ条文を読むにしても違った角度から見る姿勢を学べたと思います。また、税理士試験ではどうしても税法・会計の知識の習得に集中しがちですが、税理士となれば経営者としての思考も求められることになります。「経営事例研究」で様々な経営者の視点に触れることで、経営に対する視野を広げることができました。
これまで長い文章を書いたことがなかったため論文が書けるのか不安でいっぱいでした。しかし、LEC会計大学院では「アカデミックライティング」の授業で文章作成の基礎から学ぶことができます。基礎知識を習得した後も、主査の先生、副査の先生、ライティングの先生が毎週自分の文章を確認し、指導してくれるので、誤った方向に進みそうになった時もすぐに軌道修正がなされ、安心して書き進めることができます。
LEC会計大学院では学期ごとに懇親会を開催してくれています。普段はオンライン授業のため学生の立場としてはどうしても受け身になりがちですが、懇親会は直接先生方と顔を合わせ貴重なお話を聞けるチャンスの場となっています。また、一人で修士論文を仕上げていくのは孤独な闘いですが、私が今切磋琢磨できているのは懇親会で学生同士の交流が持てたからだと思います。懇親会で知り合った学生同士で飲み会を開くこともあり、今ではわざわざ遠方から飛行機に乗って駆けつけてくれるほどの関係となりました。大学院を卒業した後も同じ税理士として悩みを共有できる仲間との繋がりは非常に貴重なものだと思います。
今思い返せば、税理士試験を受験していた頃は税理士に登録することがゴールになっていたような気がします。しかし、LEC会計大学院で「経営学」や「職業倫理」などを通して様々な見聞を得ることで、税理士になった後どのようなことを自分がやりたいのか、税理士としてどうあるべきなのかを見つめなおし、その先の目標を見出す良い機会になったと思います。
税理士の平均年齢は比較的高く、税理士への目標をもっていた学生も社会人になって働きながら勉強できる環境が十分にあるとは言えないのが今の日本の税理士業界の実情なのではないかと考えています。せっかく将来税理士になれるであろう才能が税理士によって摘まれてしまう。これは今後の日本にとって絶対に良くない環境ではないでしょうか。労働時間と勉強時間の両立、勉強にかけられる給与水準の確保はもちろんのこと、税理士として正しい働き方を伝え、税理士がより良い税理士を育て、また新たな税理士が誕生する、そういった正しいムーブを起こせる社会に変わっていけるような活動をしていきたいと思っています。
社会人として働きながら論文を執筆するのは決して楽なことではありません。しかし、人間には誰しも平等に24時間という時間が与えられています。この時間をどう活用するかは結局のところ自分次第なのだと思います。私は大学院での生活を通して時間の使い方を身に着けることができましたが、これは税理士になった後も絶対に必要なスキルだと考えています。また、論文執筆は決して自分ひとりではできません。家族や職場のサポート、大学院の先生方や先輩方、友人など周囲の方々のありがたさを実感できたのも大学院での生活があったからです。LEC会計大学院は、税法・会計の知識だけでなく、そういった社会人として、一人の人間としてどうあるべきかを気づかせてくれる場でもあると思います。
税理士を目指すそこのあなた!LEC会計大学院で見聞を広め、より一層深みのある税理士を一緒に目指しませんか?